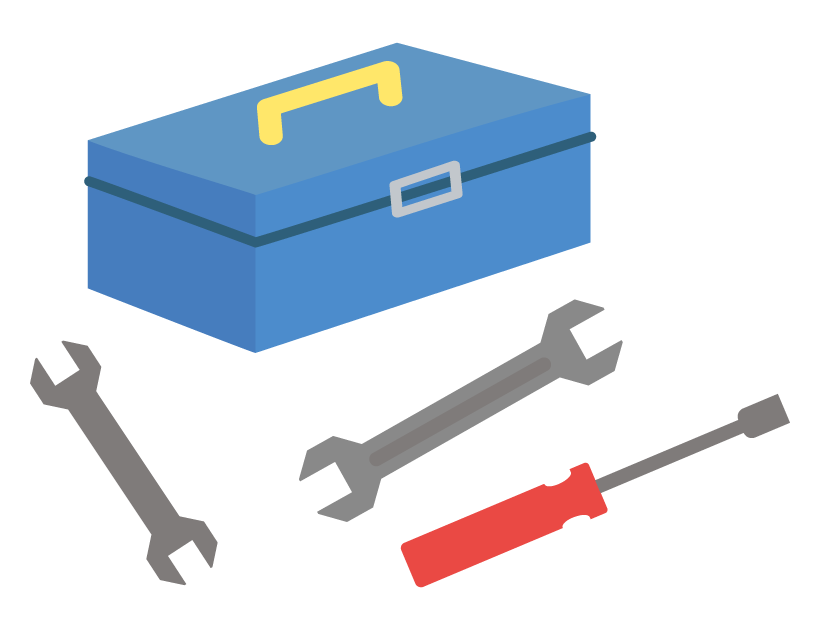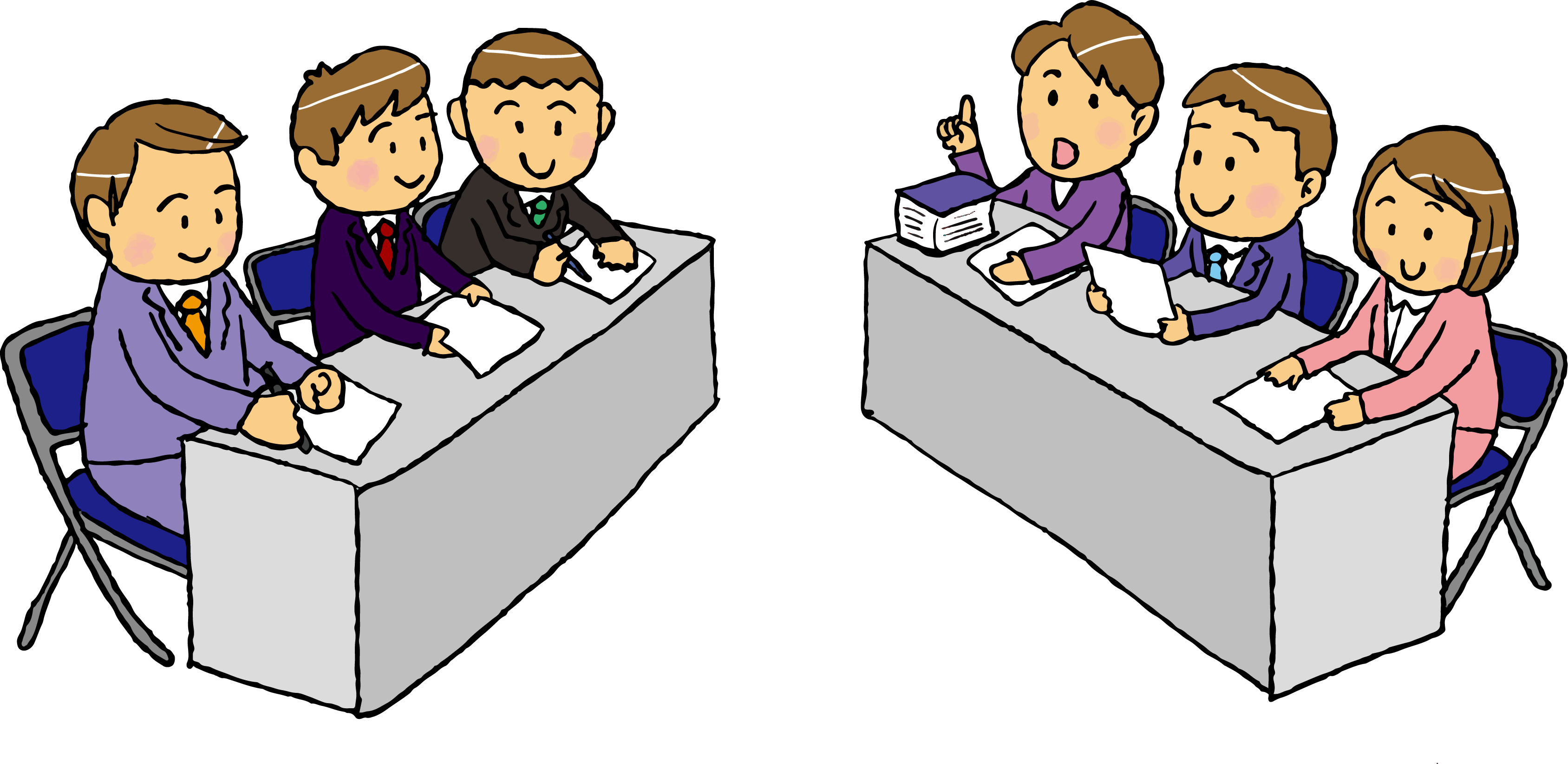【労評アート労組】1月15日団交報告!

労災事故に対する会社の安全配慮義務違反を認めさせ、
労災保険の休業給付8割+残り2割を支給させました!!
昨年3月末、アート柏支店でのトラックどうしの積み替え作業中の転落事故により、全治半年の怪我(腰椎横突起骨折)した組合員のベテランドライバーのAさん。
次の3点を求めて会社に団体交渉を申し入れました。
①労災日から3日間の休業補償支払い(労災の休業補償給付でまかなわれるのは4日目以降の分です)
②労災保険として給付された賃金の8割分に追加し、会社の安全配慮義務違反として残りの2割分の支払い
③休業中に柏支店内のロッカーから無くなった自前の工具箱の買い替え費用をレシートと引き換えに会社が支払うこと
結論は、会社は組合側からの要求内容とその主旨については概ね認め、上記3点を全額支給することで合意しました。これは労働組合として会社と交渉して勝ち取った成果です。
今回の要求の背景として、どのような事故だったのか、何が会社との交渉の争点となっていたのかを皆さんにお伝えします。
繁忙期である3月末に労災事故に遭ったAさん。労災による休業補償(残業代を含む平均賃金の8割)は受けられましたが、労災による休業補償の対象は、休んだ4日目分からなので、最初の3日分は支給されません。労災申請をした労働基準監督署の窓口の職員からは、最初の3日分は会社に請求できる、と説明を受けました。しかし、支店長にその旨を伝えても、出せないと言われました。
繁忙期の真っ只中、その日も朝から夜まで引っ越しのスケジュールが詰まっていました。Aさんは、支店の敷地内で、2台のトラックのお尻を付けて、荷物の積み替え作業を行うことになりました。その際、業務職はいつもと違うトラックの配置を運転手に指示し、その場から立ち去りました。Aさんはおかしいと思いましたが、その業務職も元ベテランドライバーであったため、何か考えがあってのことだろう、とそのまま作業を続行しました。しかしその配置では、トラックとトラックの間に隙間と段差が空いていたため、1人で何度も往復して積み替え作業をする内に、Aさんは、足を踏み外し、そのすき間に転落し、重い荷物を持ったまま、腰の一部を強打してしまいました。
転落事故の直後に、その場に居合わせた同僚が事務所に走って行き、状況を伝えましたが、業務たちの反応は鈍く、救急車を呼ぶことも病院に連れて行くことも誰も口にしませんでした。業務職が判断して仕事を調整しなければ、引っ越しを待っているお客さんや同僚に迷惑がかかります。Aさんは、しばらくうずくまった後に、痛みを堪えてゆっくりと立ち上がりました。
Aさんは、支店長の判断を仰ごうと、背中のひどいアザを支店長に見せに行きました。しかし支店長はそれを目視で確認しながらも、仕事を調整して病院に行かせるなどの判断をしなかったため、ドライバー兼リーダーでもあるAさんは仕事への責任感から、再び仕事に戻らざるを得ませんでした。
事故の後には配達と引っ越しの2件が組まれていました。いよいよ痛みに耐えられなくなってきたAさんは、途中で業務職に電話し、『もう限界です』と訴えましたが、業務職からは『頑張って』という心ない言葉が返ってきました。結局、配達は終え、引っ越しの積み込みだけを行った時点で、ようやく交代要員が手配できたと業務職から連絡が来たので、その現場までトラックを運転して行き、そこでトラックごと乗り換え、やっとの思いで支店に帰庫することができました。その日はもう病院に行けるような時間ではなかったため、翌日、休みを取って病院に行き、そこで骨折が判明しました。Aさんは、幸いにも骨の癒合が見られたため、後遺障害は残りませんでしたが、一歩間違えば、一生歩くことが困難な体になっていた可能性もあります。
さらに、半年間の休業からの復帰後に、Aさんが支店のロッカーに入れておいた、仕事で使用するための自前の工具が、工具箱ごとなくなっていました。そのため復職に際して、再び一式を買いそろえなくてはなりませんでした。このロッカーは労働者が工具や私物を入れるために使用されているものですが、以前からそのほとんどの鍵が紛失されており、鍵がかけられない状態でした。しかし会社はこれを直そうとしないため、みんなそのまま使っていたものです。
今回の労災事故について
会社には、安全配慮義務(職場における労働災害を未然に防止するための安全衛生管理上の義務)があります。また繁忙期の無理な過密スケジュールや、労災事故が起きた時の支店長の判断、その後の業務職の対応など、会社の安全教育の欠如、労災事故に対する認識の低さに問題があると組合は考えます。本人から痛みの訴えがあるにも関わらず、仕事が忙しいことを理由に次の現場に行かされたり、業務職の心ない対応により、心身ともに苦痛を強いられました。これは単に支店長や業務職個人の性格の問題ではなく、繁忙期にケガをした労働者はこのような扱いを受けるということ、これは会社にも指導責任があります。実際にAさんは今回、労災事故に遭ったことで、周囲の同僚が過去に同じように労災事故に遭い、悔しい思いをしていたことを初めて知りました。
団体交渉では、労働基準監督署に提出した事故報告書などの証拠とその場に居合わせた労働者の証言などをもって、上記の件について会社に問題提起を行い、労使双方の意見を出し合い、現場で具体的にどのようなことが起きたのか、問題の本質はどこにあるのかについて話し合いました。会社側は事実関係については概ね認めましたが「本人の努力によってその事故を回避することもできたのではないか」と主張しました。また工具箱についても、会社は『私物の管理は自己責任』だと主張しました。しかし仕事で使う工具ですから、完全に私物とは言い切れません。また会社にはロッカーの鍵を付け替えなかった管理責任があることを組合は主張しました。
さらに仕事を休み始めた時も、会社からは休業補償の手続きについて何の知らせも来なかったため、Aさんが自分で労働基準監督署や、会社に連絡して相談して手続きを勧めなければなりませんでした。また休業補償はすぐに支払われるわけではないため(アートの給料は基本給部分のみ先払いであるため)初めの2〜3ヶ月は経済的にも大変な状態を強いられました。そこに追い打ちをかけるかのように、大阪の本社からは休業中の健康保険と年金を一括で支払うようにとの請求書が毎月のように自宅へ郵送されてきたことなどから、労災事故に対する会社の姿勢を問いました。
その結果、会社は組合側からの要求内容とその主旨については概ね認め、3点の要求全額支給することで合意しました。これは労働組合として会社と交渉して勝ち取った成果です。
今回の争点は、労災事故に至る過程とその後の具体的な事象を通じて、会社に安全配慮義務違反を認めさせるところにありました。またAさんは団体交渉を申し入れる前に、個人的に支店長に休業3日目までの休業補償の支払いを求めましたが、全く応じず、また休業中にロッカー内で紛失した自前の工具箱についても、仕事で必要だからと支店長に相談しましたが、話を聞くだけで、対処はしてくれませんでした。やはり労働者の利益を守るためには労働組合が必要なのです。
引っ越しは、家具の運搬や搬入からお客様との対応まで、すべて労働者の手作業によって行われています。時には重い家電製品をもって狭い階段を上り下りしたりと、危険がつきものです。もちろん労働者も安全には気を付けて作業をしていますが、万が一、事故が起こった場合には、会社にも責任があります。アートでは、恒常的な人手不足の中、困ったときにはあちこちに引っ張り出され、繁忙期には労働者に体力の限界まで働かせておいて、動けなくなった途端に放置するなんてあまりにも冷たいではありませんか。
今回の団体交渉は、ただ単にお金が手に入ればそれで良しではなく、このようなアートの体質を変えるために、経営陣に労働者の安全について、労災事故について考えさせるために行いました。今回の団体交渉で勝ち取った成果が、アートで働く労働者の働く環境改善に活かせるよう、ブログとして、皆さんに発信していきたいと思います。
労評アート労組は、生産職が誇りを持って働ける職場を実現するために活動しています。
ぜひ皆さんの意見も聞かせてください。
会社を支え動かしているのは、私たち労働者の日々の労働です。
嫌なら辞める、泣き寝入りではなく、一緒にアートを改革していきましょう!
〇「労働組合」って会社から送られてくるハガキのこと?
いいえ、違います。あれは『架空』労組です。本来、労働組合とは、会社と独立した労働者の自治組織です。もし本当の労働組合であれば、組合大会や、会社と交渉することが義務づけられていますが、交渉をしたという事実も存在せず、労働組合としての実態もないようです。
〇なんでわざわざ会社が『架空』労組を作るの?
労働基準法では、労働者に残業をさせるための36協定の締結や、労働者の労働条件を変更する際は、職場の過半数の労働者によって組織された労働組合の代表者、もしくは労働者が選挙で選んだ労働者代表との締結が必要になります。そのために、経営者は形だけの組合とユニオンショップ協定(ユシ協定)を結び、労働者のための交渉もしない、大会も開かれない、役員選挙もしていない、そういう労働組合の実態のない架空労組とユシ協定を結ぶことで、労働者全員を入社と同時に強制加入させて、組合費も天引きしているのです。
そのような組合ではなく、労評に加入し、生産職が働きやすい職場にするために一緒に会社と交渉していきましょう!